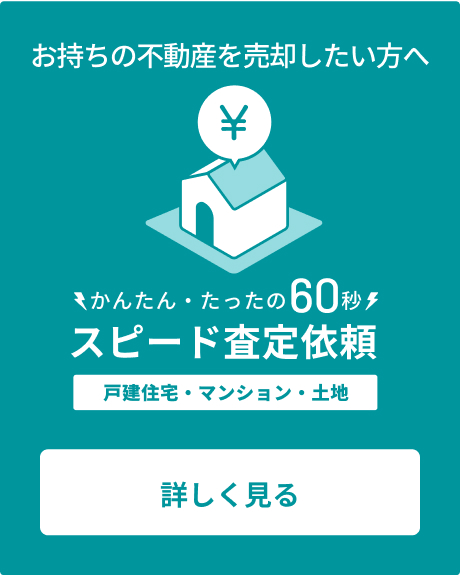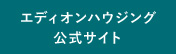前回のコラムでは,中古不動産をリフォームする際の建築基準法などによる規制についてお話をしました。
最近は「不動産投資」に関する書籍がたくさん出版されたり,セミナーや講演が行われたりしているように,親から相続した不動産や購入した中古住宅を賃貸して賃料収入を得ている方も多いように思います。
そこで,今回のコラムでは,不動産を賃貸するときにどのような契約ができるのか,不動産を売却して手放すことも視野に入れた場合にどのような契約がいいのか,について解説していきたいと思います。
ま た,今年の通常国会で120年ぶりに民法(債権法)が抜本改正されました。改正法が施行されるのは平成32年ごろを予定されていますが,契約のルールを定 めた債権法の抜本的な改正によって不動産賃貸借契約にどのような影響が生じるのかについても触れておきたいと思います。
賃貸借契約とは
不動産賃貸借契約は,貸主が目的物となる不動産の使用及び収益を借主にさせること,借主が賃料を支払うことを約束する契約です(601条)。
賃貸借契約については民法に規定されていますが,建物の所有を目的とした土地の賃貸借,建物の賃貸借については借地借家法という特別法においても規定されています。
賃貸借の存続期間
現行民法では賃貸借の存続期間の上限は20年とされています(民法604条)。
もっとも,借地借家法では,借地権については存続期間は30年とされていますし(借地借家法3条),建物の賃貸借については上記の民法604条の規定は適用されないため,20年を超えた存続期間を定めることができます(借地借家法29条)。
この点,改正債権法では賃貸借の存続期間の上限を50年とすることで,賃貸借全般に関して経済活動上の規制を排除しつつ,所有者に過度な負担にならないよう配慮しています。
賃貸借の更新
また、建物の賃貸借契約の更新については借地借家法26条及び同28条に規定されていますが,建物の賃貸人からの更新拒絶,解約申し入れは,いわゆる「正当事由」が必要となります。
賃貸人からの更新拒絶,解約申入れによる賃貸借契約の終了には,借地借家法28条により「正当事由」が必要とされています。
「正当事由」の判断基準として,借地借家法28条は,
・当事者双方が建物を使用する必要性(賃借人が高齢で引っ越し先を見つけることが困難などの事情)
・借家に関する従前の経過(賃料滞納の有無などの事情)
・建物の利用状況(店舗利用か居住目的利用か)
・建物の現況(築年数など老朽化,建替えの必要性の程度)
・財産上の給付をする旨の申し出(いわゆる立退料の有無,金額の多寡)
を考慮するとしています。
このように,借地借家法は賃借人の保護を目的とした規定が多いため,賃貸人としては更新拒絶,解約申し入れをして,自身や家族が不動産を使用しようと思っても解約できないということが想定されます。
定期建物賃貸借契
そ こで,建物の賃貸借については,定期借家契約というものがあります(借地借家法38条)。これは,期間の定めのある建物賃貸借で,かつ,契約の更新がな く,公正証書等の書面で契約されるものをいいます。建物のオーナーからすれば,当初から契約していた期間が満了することで確実に契約が終了するので,建替 え予定のある建物や,転勤で空き家になっている自宅などの物件も容易に貸すことができることになります。
もっとも,借りる側からすると,契約の更新ができず期間の満了によりおのずと引越ししなければならなくなるデメリットがあるので,一般的には,定期借家契約の場合は,普通建物賃貸借契約よりも低い水準で賃料を設定することが必要となります。
賃貸人たる地位の移転
不動産を賃貸したものの,賃貸借契約の存続期間の途中で不動産を売却すると賃貸借契約はどうなるのでしょうか。
現 行民法では明記されていませんが、判例では,賃借人が対抗要件を備えている,すなわち,建物賃貸借において建物の引き渡しを受けている場合で,賃貸人が不 動産を売却したときは,賃貸人としての地位も不動産の譲受人に移転し,それまでの賃貸人は賃貸借契約の当事者ではなくなるとされています(大判大正10年 5月30日)。
そして,改正債権法では,この判例法理が明文化されています(法案605条の2第1項)。
では,賃貸人が不動産を売却したあとも,従前通り,賃貸人として賃料を得ることはできないのでしょうか。
現行民法においては、賃借人の承諾があれば賃貸人の地位をそのまま留めることで,不動産を売却したあとも賃料収入を得ることができます。
そして,この点について,改正債権法の法案605条の2第2項は,
・賃貸人の地位を留保することの、譲渡人・譲受人間での合意
・譲渡人・譲受人間の賃貸借契約の締結
を要件として賃貸人の地位の留保を認めています。そのため,改正債権法においては賃借人の承諾がなくとも賃貸人の地位をそのまま留めることが可能になると思われ,賃貸人は賃料収入を引き続き得ながら,不動産を売却することが容易になると思われます。
敷金
敷金については、現行民法に定義や敷金返還請求権の発生要件を定めた規定はありませんでした。
そこで,改正債権法では,敷金について,「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されました(法案622条の2第1項)。
また,敷金返還請求権についても,①賃貸借が終了し,かつ,賃貸目的物を返還したとき,または②賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき,に発生するとされました(法案622条の2第1項)。
そ の他にも賃貸借関係において債権法改正がなされましたが、契約内容などを吟味せず所有する不動産を安易に賃貸してしまうと、結局自分が使いたいときに使え なかったりしてしまいます。また、賃借人の資力などをよく確認せず賃貸したため賃料が回収できなかったり、物件に汚損破損を加えられたりすれば資産そのも のの価値も下落してしまいます。
不動産を賃貸する際には将来のことも見据えて慎重に検討することが大切ですね。
以上
この記事を書いた人
吉山 晋市(よしやま しんいち)
弁護士法人みお綜合法律事務所 弁護士
大阪府生まれ 関西大学法学部卒業
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士が在籍する綜合法律事務所で,企業法務,不動産,離婚・相続,交通事故などの分野に重点的に取り組んでいる。

| << 前へ | 最新記事一覧へ戻る | 次へ >> |